 🔰リサーチャーまるお
🔰リサーチャーまるおYouTubeのアルゴリズムってまた変わったんすか?



めちゃくちゃ変わってるよ!どこが変わったか、どうすればいいか、この記事で見ていこう!かなり重要だよ。
✅ 最新のYouTubeのアルゴリズムを知りたい
✅ YouTubeの再生回数が突然落ちたけど、原因が分からない…
✅ クリック率や視聴時間を増やしているのに、なぜか伸びない
✅ チャンネル登録者が増えても、動画の反応がイマイチ
✅ ショート動画で再生されても、本命のロング動画に繋がらない
これからの時代はYouTubeを効果的に使えるかどうかにかかっています。「知りたいことがあれば、まずYouTubeで調べる」──そんなユーザーが増えているからです。
実際、YouTubeの視聴者の57%が、Googleのような検索エンジンとしてYouTubeを活用しています。世界的に見ても、YouTubeは、Googleに次ぐ世界第2位の検索エンジンになっています。
YouTubeは動画を見るだけの場所ではなく、情報収集のための検索ツールとしても使われているのです。
そんな世界2位の検索エンジンに自分のコンテンツを投稿することで、個人起業家は有力なリストを集めることができます。
その時に重要になるのが「アルゴリズム」です。あなたの動画が多くの人に見られるかどうかは、YouTubeのアルゴリズムにかかっています。
2025年にYouTubeのアルゴリズムは大幅に変わり、今までの感覚でYouTubeのアルゴリズム対策をやっても、効果が薄くなる可能性があります。
この記事では、2025年以降のYouTubeの最新アルゴリズム対策を、実際のYouTubeの公式見解や、YouTubeのSEOツール「VidIQ」の見解などを踏まえて、解説していきます。
この記事のハイライト
・今までのYouTubeアルゴリズムはクリック率や視聴時間の長さなどを重視していたが、今後は「視聴者個人の満足度」が一番重要になる。つまり、「この人が今、見たくなるコンテンツを届けること」が最重要
・AIの進化によって、「そのユーザーが見たくなる動画」を細かく分析できるようになり、その動画に対する視聴者の「満足度」も計測されるようになった。
・今後は「再生数」や「クリック率」などをバラバラに見るのではなく、全体を通して「視聴者を満足させているか」という観点で見る必要がある。
・今後のYouTubeでは、ニッチにペルソナを絞り、「この1人の人に響く動画は?」という観点でYouTubeに取り組む人が勝つ。
今までのアルゴリズムはクリック数や視聴時間などを重視
今までのアルゴリズムは「クリック数」「再生数」「視聴時間」など、動画の成果を数値で測る指標をメインに使っていました。
昔のYouTubeは、まず「とにかく多くの人に見てもらう」ことが最優先だったので、「クリックされた回数が多い動画=人気のある動画」とみなして、「多くクリックされた動画はさらに多く再生される」という流れになりました。
ところが、「クリックされればいい」と考える人が出てきて、タグの乱用や、誤解を招くサムネイルなど、質の低い動画が出てくるようになりました。
2012年になると、アルゴリズムは大きく方向転換し、「どれだけ長く動画を見てもらえたか=視聴時間」を重視するようになりました。これは、動画の中身の質を重視するためにやったことでした。
しかし、今度は「中身の薄い長時間の動画」や、「再生回数の不正操作」などの問題が生まれました。
こうした課題に対応するため、2015年から2016年にかけて、再びアルゴリズムは見直されました。この時期からYouTubeはアンケートを活用して「どんな動画が視聴者にとって満足感が高いのか?」を把握し始めたのです。



本当の意味で「視聴者が満足する動画」を追求するようになったんだね
さらにAIの技術が進化したことで、「多くの人が見ているからおすすめする」のではなく、「その人自身が興味を持ちそうな動画を提案する」システムが形になってきて、今回のアルゴリズムのアップデートで完成度が高まりました。
2025年アルゴリズムは「満足度」を最も重視する!
2025年からは、単に視聴時間が長いだけではなく、視聴者が「価値を感じたか」「満足したか」といった、人の感情に寄り添った判断が重視されるようになりました。
そのため、YouTubeのアルゴリズムは、次の2段階で「その人に今ぴったりの動画」をおすすめしています。
ステップ①:動画自体の評価
⇒再生数、クリック率、視聴維持率などのデータを分析して、動画の成果を数値で測る。
ステップ②:ユーザーとの相性を分析(満足度の高そうな動画を選ぶ)
⇒ユーザーの過去の視聴履歴や、動画に対する反応から、関心が高まりそうな動画を選ぶ。



今までは上記のステップ①を重視してたけど、今後のYouTubeアルゴリズムはステップ②を重視するんだよ。
そして、満足度は、公表されている中では、次のような指標で測られます。
YouTubeアルゴリズムが視聴者の満足度を測る指標
• アンケート調査: YouTubeは視聴者に「この動画は満足できたか?」というアンケートを実施し、その結果をアルゴリズムに反映させる
• 「高評価」「低評価」: 動画の好感度を示す指標として利用する
・「興味なし」: 視聴者が「この動画はおすすめに出さないでほしい」と設定した場合、アルゴリズムが学習する
その他、「チャンネル登録されているか」「同じチャンネルの他の動画も連続して見ているか」なども考慮されると言われています。
「これだけ見ればOK」という指標はない



クリック率も低いし、視聴時間も短いし・・頑張ったのにショックっす



数値を単独で見ると凹むこともあるよね。しかし、今のYouTubeアルゴリズムだと、必ずしもそれらが悪い結果とは限らないよ
多くの動画クリエイターは、「クリック率が10%に届かない」「視聴時間が5分未満…」そんな結果を見ると、「やっぱり失敗だった」と落ち込んでしまいがちです。
しかし、YouTubeのアルゴリズムにとっては、クリック率や視聴時間はあくまで「参考データの一つ」にすぎません。
今、最も重視されているのは、
・その動画を見た人がどんなタイプで、
・その人と似たタイプの視聴者はどんな動画を好んでいるのか
という点です。
YouTubeのアルゴリズムは「どれくらいクリックされたか」ではなく、「誰に刺さったのか」を見ています。だからこそ、個々の数値の平均だけを追っていては、本質を見失ってしまいます。
たとえば、クリック率が3%と低くても、特定の層に強く響く動画なら数千回再生されることもあります。一方で、クリック率が7%あっても、視聴維持率が悪ければ再生数は伸びません。
つまり、「どんな指標が正解か」は一律ではなく、「視聴者によって正解が変わる」というのが、今のアルゴリズムです。
だからこそ意識すべきなのは、「自分のコア視聴者にとって心に刺さる動画を作ること」になります。
自分を押し出すのではなく「今必要とされる動画」を届ける



YouTube公式は「Push型ではなくPull型の動画を作ろう」というふうに言っているよ。



何すか、それ?



Push型は「自分の動画を視聴者に猛プッシュする」という発想で、Pull型は「自然と視聴者を引き付けるような動画を作る」という発想なんだ。
2025年以降のYouTubeで成果を出すには、単に「自分の動画をどう広めるか」という発想よりも、「今、視聴者が求めているものは何か?」を考えて動画を作ることが求められます。
視聴者がYouTubeを開いた瞬間、アルゴリズムは「この人が今、最も見たがっている動画は何か?」を予測します。動画そのものを売り込もうとするのではなく、視聴者一人ひとりの好みや傾向をもとに、「ぴったりの動画」を選び出すのです。
つまり、「動画を視聴者にアピールする(push)」のではなく、「視聴者がいて、それにピッタリの動画を引っ張ってくる(pull)」というアルゴリズムなのです。
したがって、クリエイターが目指すべきは「大勢に広く届ける動画」ではなく、「理想の視聴者にとって、どうしても見たくなる一本」をつくることです。
その視聴者に届けば、あとはYouTubeが同じようなタイプの人たちにも広げてくれます。
再生時間は長ければいいものではない
YouTubeには「もっとコンパクトに要点を伝えてほしい」「時間をムダにしたくない」といった視聴者の声が多く届いており、アルゴリズムもそのフィードバックを反映するように進化しています。
もちろん、視聴時間は今でも重要な指標のひとつですが、あくまで「参考データのひとつ」であって、最終的に評価の中心になるのは、何度もお伝えしているように「視聴者の満足度」です。



「長く視聴された動画=価値がある」とは限らないよ
たとえば、ある視聴者が1時間の動画を5分だけ視聴して一度離脱したものの、翌日また続きから5分間見た場合を考えてみましょう。総再生時間だけを見ると、「1時間の動画でたった10分しか視聴されなかった」ということになります。
単なる「視聴時間の長さ」では測れないユーザー行動が、今ではより正確に評価されるようになっているのです。
しかし、「離脱した後、また次の日に同じ動画の続きを見ている」という行動を、今のYouTubeのアルゴリズムは「この人は動画を2日連続で見ている。それだけこの動画に満足しているんだ」と解釈するのです。
たとえば、5分でも必要な情報をわかりやすく伝える動画と、20分かけても中身が薄い動画があるとすると、今のYouTubeのAIは、前者のような「短くても満足度が高い動画」をしっかり評価できるようになっています。
もちろん、「短ければいい」というわけでもありません。理想の長さは視聴者によって変わります。要は、視聴者が満足するのに必要な動画の長さであればいいのです。
AIがさらに細かく進化している
YouTubeのアルゴリズムは、LLM(大規模言語モデル)の導入によって、動画の内容をこれまで以上に深く理解できるようになりました。
これまでは「ダンス動画が好き」というレベルの認識だったものが、今では「サルサが好き」「テンポの速い曲が好み」といったより細かい嗜好まで把握できます。
料理動画であれば、その料理が「初心者向け」か「本格派」かあるいは「栄養重視」かといった細かい特徴をAIが理解し 視聴者の好みに合わせてお勧めしてきます。
視聴者は「単なるダンスの動画」「単なる料理の動画」よりも「 自分が本当に見たいダンスの動画」「自分にピッタリの料理の動画」を見つけることができるようになりました。
そんなYouTubeのAIは、動画を次の3つの観点から細かく解析します。
① トピック(内容)レベル
単に「料理動画」として認識するのではなく、「インド料理で、スパイス好きな人向けの、初心者向けの、元気な語り口の料理動画」といったように、細かく識別する。
② プレゼンテーション(話し方)レベル
話すスピード、トーン、感情表現が、視聴者の好みや期待に合っているかを判断する。
③ プロダクション(制作)レベル
編集スタイルや動画の構成が、視聴者の視聴傾向とどれだけマッチしているかを見る。
つまり、あなたの理想の視聴者のペルソナを、この3つの観点からしっかり理解する必要があるのです。それができれば、あなたの動画はより高い確率で「その人に引き寄せられる」ようになります。



とはいえ、これを実現するには「誰がペルソナか」がはっきりしていることが前提だよ
「理想の視聴者のペルソナ」とは、単に「年齢」「性別」「住所」みたいな属性だけでなく、
・どんな悩みを抱えていて
・どんなシチュエーションで動画を見るのか
・どんな言葉に心を動かされるのか
までを想定しましょう。そこで初めて、的確なコンテンツが作れるようになります。
個人起業家がYoutubeでやるべきこと



これらのアルゴリズムの変化を踏まえて、個人起業画家YouTubeでやるのにおススメの方法を解説していくよ。
YouTubeのアルゴリズムが進化した今、クリエイターとしては、 「自分の動画がどう分類されているか」「誰に届けられているか」を意識することが必要です。
そして、「どんなテーマなら、もっと興味を持たれやすいか」を掘り下げていきましょう。
そのうえで、下記の対策をとってみましょう。
ニッチテーマに全体を統一する



まずは、早い段階でニッチを決めて、それに絞ろう!
ニッチとは、「需要があるけど競合が少ない、大手企業がやってないような隙間のジャンル」です。自分が情熱を持っていて、なるべくニッチなジャンルにすると、競合が少なくなり、うまくいきやすくなります。
ニッチの選び方が分からなければ、まずはTikTokやインスタで動画を投稿してみましょう。そこで反応が良かった動画を元にYouTubeに動画を投稿すると効果的です。
さらに、YouTubeチャンネルアナリティクスの「視聴者」タブを活用して、 どんな動画が反応を得ているかを確認し、似た動画を継続的に発信していくといいでしょう。
ジャンルは途中で変えない
そして、ニッチなジャンルを決めたら、なるべく途中で変えないことがコツです。
Youtubeでは、新しく作られたチャンネルが動画を投稿すると、まずは色々な視聴者層にその動画をお試しで表示して、どの層がよく反応するかをテストします。
そして「この視聴者グループとは相性がいい」と判断されると、今後の動画もそのグループに継続的に動画がおすすめされる仕組みになっています。
よって、途中で動画のジャンルをガラッと変えてしまうと、以前の視聴者層に違うジャンルの動画を表示させてしまうため、満足度が下がってしまうことになります。



どうしても途中で変えたくなったらどうすればいいっすか?



もし途中で大きく方向転換したくなった場合は、新しいチャンネルを立ち上げるのがいいよ。
また、幅広いジャンルを扱いたい場合は、共通した「枠組み」を考えるといいでしょう。
YouTubeの公式インタビューで言われている事例をあげると、Doctor MikeやLegal Eagleといった人気チャンネルでは、映画、リアクション、インタビュー、時事ネタなど幅広い形式の動画を投稿しています。
一見、ジャンルがバラバラに見えますが、すべてが「医師の視点から」「弁護士の視点から」という統一された枠でつながっているのです。
広くやりたい場合でも、「誰の視点で語るか」「どんなテーマで統一するか」が明確であれば、チャンネルとしての軸はぶれないということです。
視聴者の旅を設計する



「視聴者の旅」って何すか?



動画の動線を作るっていうことだよ。動画を見た人が次の動画に自然と誘導されるように設計しよう、ということだね。
ただ単に1本の動画を作るのではなく、視聴者が次の動画へと自然に進んでいくような流れを作る。これを「視聴者の旅(Viewer Journey)」と呼びます。
例えば、以下のように段階的に構成すると効果的です:
検索やおすすめで出会う動画
視聴者の興味を深める・共感を生む動画
商品やサービスの紹介・購入や登録につなげる動画
「次はこちらを見てね」と自然に誘導できるよう、サムネイルやタイトルをシリーズ化するのも有効です。最初の動画と関連性を持たせることで、視聴者は「流れ」の中で次の動画に進みやすくなります。
ストーリー性でショート動画からロング動画に誘導する
ショート動画からロング動画へスムーズに視聴者を移行させると、YouTubeの評価も高まり、あなたの商品やサービスの購入にもつながりやすくなります。
スムーズに誘導するポイントは「感情を動かすこと」です。視聴者は「自分がもっと知りたい」「続きが気になる」と思ったときに行動します。
そのコツは、
・ショート動画では、話の核心を少しだけ明かし、「知りたい」で終わらせる
・ロング動画でその伏線を回収する(満足を与える)
という形式にすることです。
「続きを知りたい!」「もっと詳しく知りたい!」という感情を引き出せれば、自然とロング動画に誘導できます。



ただし、ショート動画も、動画単体で「完結した内容」にはしておこう。意味不明な動画だと逆効果になるので、これはこれで動画として成立したものにしよう。
再生数が落ちてきたときにやること



「1〜2年前と比べて再生数が落ちたな・・」と思ったら、まずは以下の点をチェックしてみよう!
長期的なデータを見る
「1〜2年前と比べて再生数が落ちた。アルゴリズムが変わったのでは?」と気になったときに、YouTube公式がおすすめしているのは、「長期的なデータを見ること」です。多くの人が「直近1ヶ月」のデータだけで判断してしまっているからです。
アナリティクスの表示期間を「過去3ヶ月」に切り替えてみると、例えば、「実は少し前に動画がバズって、平均再生数が上がっていただけだった」ということも多いのです。
長期的に見れば、落ちたのではなく「以前が一時的に上がっていただけ」だったと気づけます。
さらに「過去3年」のデータも見れば、スポーツのシーズン、学校行事、連休などの「季節的な変動」も再生数に大きく影響していることがわかります。
これを把握していれば、「下がる時期」を見越して事前にまとめ撮りや更新スケジュールの調整も可能になります。
再生回数の変化は視聴者の変化
さらに、YouTube Studioのオーディエンスタブで「視聴者が今、他にどの動画やチャンネルを観ているのか」をチェックしてみると効果的です。
そこに新しい競合チャンネルが並んでいたら、それが原因で自分の動画が相対的に見られなくなっている可能性もあります。
結局のところ、再生回数が落ちているときは、視聴者層の見る動画のパターンが変化しただけ、というケースも多いのです。
そのパターンの変化は天気みたいなものなので、天気予報を見て、天気に合わせて服装を変えたり、傘を持って行ったりするのと同じように、アナリティクスを見て視聴者の傾向を掴むことが大事になります。
コメントがこれまで以上に重要になる



YouTubeのアルゴリズムは満足度を重視するようになったので、これまで以上に「コメント」は重要になるよ
YouTubeは今後、以下のようなコメント関連の指標を重視すると思われます:
・動画にどれくらいコメントがついているか
・投稿者がコメントにどれだけ返信しているか
・コメント欄でどんなコミュニケーションが生まれているか
これらは「視聴者とのつながり=エンゲージメントの高さ」を示す大きなヒントになります。
そのため、下記のようなアクションを取ると効果が見込めます:
✔ すべてのコメントに返信する
視聴者の行動にきちんとリアクションすることで、アルゴリズムからの評価も高まります。
✔ コメントしたくなる“きっかけ”を動画内で作る
⇒「〇〇について質問があれば、ぜひコメント欄で教えてください!できる限りお返事します」
⇒「この動画についてどう思いましたか?ご意見をぜひコメントで教えてください!」
チャンネル登録者が動画を見ているか確認する
YouTube登録者数82.7万人のSNSマーケッターRobert Benjamin氏は「チャンネル登録者が新しい動画を見ていないという現象に注意しろ」と言ってます。
登録者が多くても、その登録者が動画を見てなければ、YouTubeにとってマイナスのシグナルになります。「登録者ですら見ていないなら、他の人に見せても意味がないよね」とアルゴリズムは判断するのです。
その場合、「登録者が動画を見ていない=おすすめに表示されなくなる」ということになります。特に、小規模のチャンネルは注意したほうがいい問題です。
登録者数と再生数にあまりにも差があって、登録者が見ていないと感じたら、新しい動画をアップロードするときの「通知をOFFにする」という設定をしたほうがいいでしょう。
「『アップロードしましたよ』と通知を出したのに、登録者が見ていない」という状況が、アルゴリズムにマイナスの印象を与えるからです。
既に公開済みの動画では通知をOFFにできませんが、これからアップロードするときの動画であれば、下記の手順で通知をOFFにすることができます。


![チャンネル登録者が動画を見ているか確認するライセンスの下の「[登録チャンネル]フィードに公開してチャンネル登録者に通知する」のチェックを外す](https://www.active-note.jp/wp-content/uploads/2025/05/4a2fd4b539f4a4856563a6e7e5f2e2f0.jpg)
![チャンネル登録者が動画を見ているか確認するライセンスの下の「[登録チャンネル]フィードに公開してチャンネル登録者に通知する」のチェックを外す](https://www.active-note.jp/wp-content/uploads/2025/05/4a2fd4b539f4a4856563a6e7e5f2e2f0.jpg)
本物のタイトルをつける



「本物のタイトル」って何すか?



煽って目立つだけの「釣りタイトル」をやめよう、ということだよ。
一部のクリエイターは、キーワードを詰め込んだり、目を引くためだけの「釣りタイトル」を使ったりして、再生数を稼ごうとする人もいます。
しかし、YouTubeのアルゴリズムが「視聴者の満足度」を重視するようになった今、この方法は悪影響を与える可能性が高いです。
そもそも、YouTubeの利用規約やコミュニティガイドラインでは、「スパム・詐欺・誤解を招く行為」を禁止しています。
そして、過度に煽った動画で再生されたとしても、中身が期待してたものと違って、視聴者の満足度が下がる可能性もあります。そのような動画は、視聴維持率が低下し、アルゴリズムからの評価も下がってしまいます。
結局のところ、動画に合った正直で魅力的なタイトルをつけるのが一番です。誠実なタイトルは視聴者の信頼を得られ、リピーターにもつながります。
各画面のアルゴリズムと対策



ここからは、各画面の細かいアルゴリズムと対策を見ていこう!
ホームページ(Home Page)
YouTubeのホームには、主に次のような動画が表示されます
・視聴履歴に関連する動画
・登録しているチャンネルの新着動画
・エンゲージメント(視聴時間・高評価・コメントなど)が高い人気動画
視聴者のホームページ画面に動画を表示してもらうには、まずはあなたの動画を一本見てもらって、視聴履歴にあなたのチャンネルを残すことが重要です。
一回履歴に残れば、その後の動画がホーム画面に表示されやすくなり、リピートで視聴されるチャンスが格段に増えます。
そして1回表示されるのに必要なことは、まずは「理想の視聴者のペルソナ」を設定し、「この人が知りたいことは何か?」「関心が高い話題は何か?」を考えることです。
また、ホーム画面は、過去の人気動画だけが表示されているのではありません。「今、この瞬間に、この人に一番合う動画は何か?」「今、この瞬間に関心が高い動画はなにか?」という視点で選ばれます。
「今、この瞬間に」という部分がポイントです。これは、YouTubeのアルゴリズムは、季節や時事トレンドにも敏感だということです。
夏が近づけば「ダイエット」や「旅行スポット」の動画が伸びたり、年末になれば「大掃除」「おせちレシピ」「正月の過ごし方」などの、季節に関係するテーマも伸びます。
理想の視聴者の「興味・関心・悩み」と「季節やトレンド」を踏まえて、「今、この瞬間に、視聴者の関心が自然と高まるテーマ」を選ぶことが、ホームページや関連動画として表示される近道となります。
おすすめ動画(Suggested Videos)



YouTubeを見ていると、再生中の動画の右側(PC)や下部(モバイル)に表示される「おすすめ動画」に目が留まることがあるよね。 この部分のアルゴリズム対策を見ていこう!
「おすすめ動画」の部分に表示される動画は、以下のような情報をもとに選ばれています。
・視聴者がいま見ている動画と関連性の高い動画
・登録しているチャンネルの新着・人気動画
・過去の視聴履歴や検索の傾向
・同じ動画を見た他の視聴者が、続けてよく視聴した動画
つまり、YouTubeはユーザーの行動をもとに、「ユーザー専用のおすすめ動画リスト」をその場で作っているのです。
おすすめ動画の欄に自分の動画を載せるには、アルゴリズムに自分の動画を「この動画も関連性が高い」と認識してもらう必要があります。
そのためには、「おすすめ欄のライバルの動画を観察する」という方法がおすすめです。
自分と同じジャンル・テーマの人気動画を開いて、その右側に出てくる「おすすめ動画」をチェックしてみましょう。
- どんなタイトルか
- どんなサムネイルか
- どんな内容か
- 動画の時間はどれくらいか
- どんなトーンで話しているか
そういった点を分析したうえで、同じ切り口で「自分の視点や表現、体験を加えた自分バージョンの関連動画」を作ると、アルゴリズムが「この動画を見た人は次にこれを見るかも」と判断してくれます。



もちろん、丸パクリはダメだよ
ポイントは「アルゴリズムが関連動画として認識てくれるポイント」を見つけたうえで、オリジナリティを加えることです。
そうすることで、そのライバル動画を見た人のおススメ欄に、自分の動画も表示される可能性が高まります。
検索(YouTube Search)



YouTubeで検索をした時の「検索画面」のアルゴリズム対策を見てみよう
YouTubeの検索画面で上位に表示されると、新しい視聴者に見つけてもらう可能性が高くなります。
そして検索から入ってきたユーザーがその動画に満足すれば、そのまま別の動画も視聴してくれる可能性が高まり、アルゴリズムはその動画やチャンネルを「優良」と判断して、さらに動画をたくさん表示してくれます。
YouTubeのアルゴリズムは「キーワード+エンゲージメント+関連性」で検索結果を決めてます。
具体的には、ユーザーの検索キーワードや行動履歴をもとに、膨大な動画の中から候補を選び出し、その上で、以下の2つの指標に基づいて、表示順位を決定します。
・エンゲージメント指標:視聴数・いいね・コメント・シェア・視聴維持率など
・検索キーワードとの関連性:タイトル・説明文・タグ・動画内音声の内容など
つまり、「キーワードが合っているだけ」では不十分で、視聴者の好みの動画との「関連性」や「視聴者からの反応」が良い動画が上位に来ます。
もちろん、タイトル・説明・タグに適切なキーワードを入れることは基本ですが、そこに「視聴者の関心や思考パターンを把握し、高評価がもらえる動画を作る」ということが必要になります。
YouTubeは検索画面に有名なチャンネルの動画や、同じような動画ばかり並ばないように、新しい動画もランダムに表示します。
たとえ、まだ知名度が低くても、動画の質とキーワード設計次第では、十分に検索上位表示を狙うこともできるのです。
ショート動画
ショート動画のアルゴリズムは通常の動画と異なります。
YouTubeのプロダクトシニアディレクター、Todd Sherman氏はCreator Insiderで次のような趣旨のコメントを言ってます:
「ロング動画はユーザーが自分で選ぶコンテンツ。ショート動画はスワイプして『偶然出会う』コンテンツ。だからこそ、評価基準も変えているのです。」
SNSマーケティングサイトloomlyを参考に、ショート動画が評価される基準をシンプルにまとめると、次のようになります。
・表示されたうち、どれだけ視聴されたか?(視聴率)
・スワイプ(スキップ)された回数
つまり、視聴者がどれだけ最後まで見たか、どれだけリプレイされたかが非常に重要になります。
その際に、特に大事なのは「最初の数秒の反応」です。
最初の数秒で「いいな」と思わせて、テンポよく最後まで進んで、何回も見たくなるような内容にすることがポイントです。
そのためには、こういう動画を作ると効果的です:
・最初の数秒で「引き込むビジュアルフック」
・スワイプされずに視聴されるテンポ、構成、フックをつける
・繰り返し観たくなる、保存したくなる内容にする
YouTubeアルゴリズムを何度も復習あなたへ
あとからいつでも見返せる、小冊子をご用意しました!
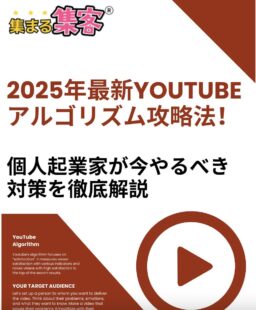
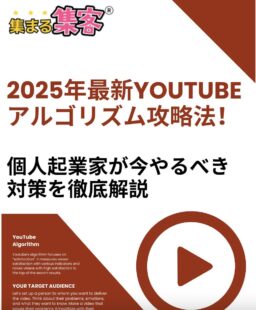
よくある質問(FAQs)
- 2025年のYouTubeアルゴリズムでは、何が最も重視されているのですか?
-
視聴者の「満足度」が最重要視されています。従来のクリック率や視聴時間よりも、「誰に刺さったか」「見た後にどう感じたか」という満足度が評価対象になります。
- 視聴者満足度はどのように測られるのですか?
-
単なる再生時間ではなく、アンケート調査や、高評価・低評価・コメントなどのエンゲージメント、視聴後の行動など、多角的に分析されます。
- クリック率や視聴時間はもう関係ないのですか?
-
無関係ではありませんが、それだけを見ても判断できません。これらは参考にする数値の「一部」であり、最終的には「視聴者が満足したかどうか」が重視されます。
- ニッチなテーマに絞った方がいいのはなぜですか?
-
アルゴリズムは「誰に刺さったか」をもとに動画をおすすめするため、一貫したジャンルの方が視聴者とのマッチ率が高くなり、チャンネルの評価も上がりやすくなります。
- ジャンルを変更したい場合はどうすればいいですか?
-
大きく方向性を変える場合は、新しいチャンネルを立ち上げるのがベストです。もしくは「個人起業家から見た〇〇」などの、統一したテーマで広げる方法もあります。
- 再生数が急に落ちた場合、どこをチェックすべきですか?
-
コメント数や視聴者維持率などのデータを確認するとともに、チャンネル内で視聴者層にずれが生じていないかも見直しましょう。
まとめ
クリック率(CTR)や視聴時間といった指標は依然として重要ですが、今のYouTubeが本当に重視しているのは「視聴者満足度」です。
YouTubeのアルゴリズムは、人気や知名度に左右されるのではなく、「その人にとって一番良い動画を届ける」という目的で動いています。
つまり、アルゴリズムに向けて動画を作るのではなく、たった1人の視聴者を深く理解し、その人が心から「見てよかった」と思える動画を届けることです。その瞬間、アルゴリズムはあなたの最大の味方になります。
そのために必要なことは、「たった一人の理想のお客様のペルソナを決めること」です。2025年以降のYouTubeアルゴリズム対策は、ここから始まります。
しかし、「ペルソナが決められない」「何となく決めてはいるけど、まだ甘い気がする・・」そう思ったことは無いですか?
ペルソナを設定するのに苦手意識を持っている人は、「個人起業家専用AI:Buddy@i」を使うことをお勧めします。
たとえ、あなたの見込み客のペルソナが漠然としていたとしても、AIのガイドに従って整理していくだけで、ものすごく具体的になり、マーケティングしやすいペルソナに変わります。
さらに、「その理想のお客様が、あなたのサービスでどう変わるのか?」を「心に響くストーリーで伝える」こともできます。
個人起業家専用のAIで「たった一人の理想のお客様」と「その理想のお客様に響くストーリー」を描く、そのポイントを下記の記事で解説しています。興味がある人は、下記のページをご参照ください↓↓
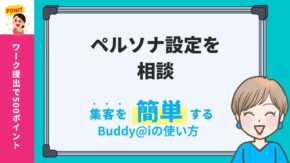
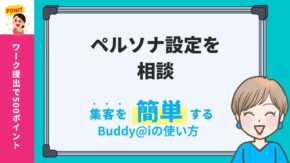
この記事を読んだ方にはこちらの記事がおすすめです
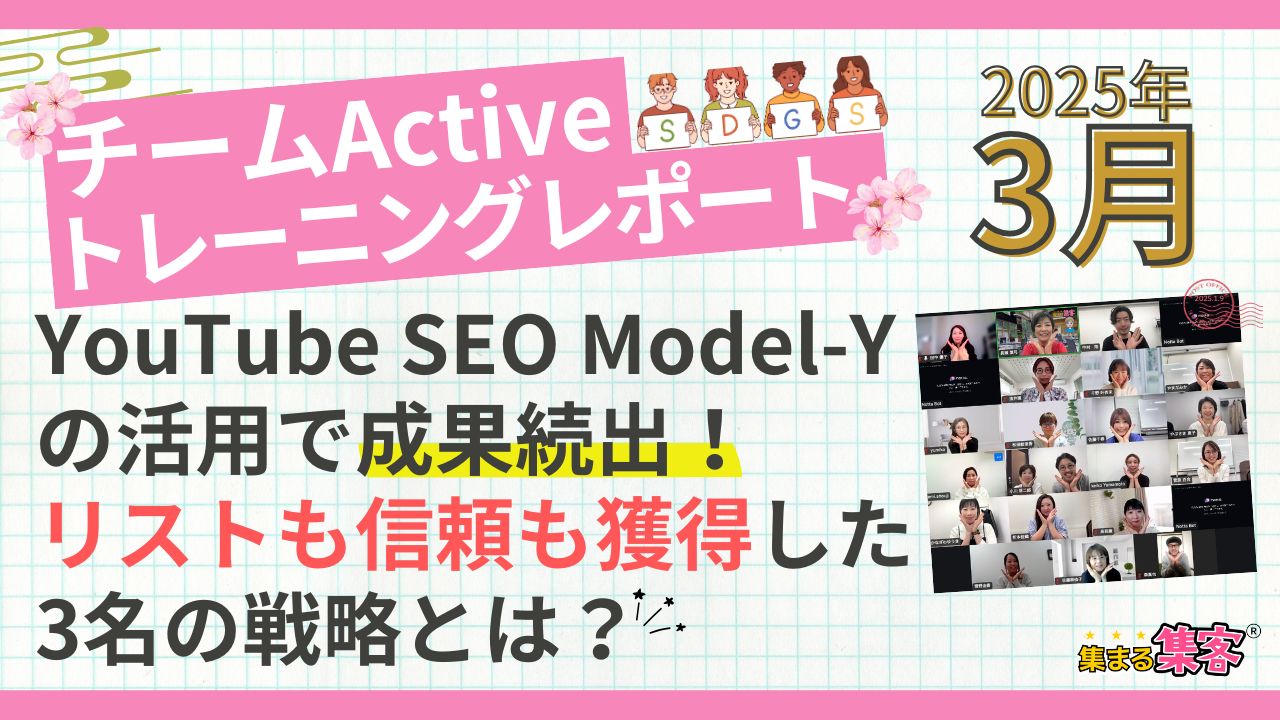
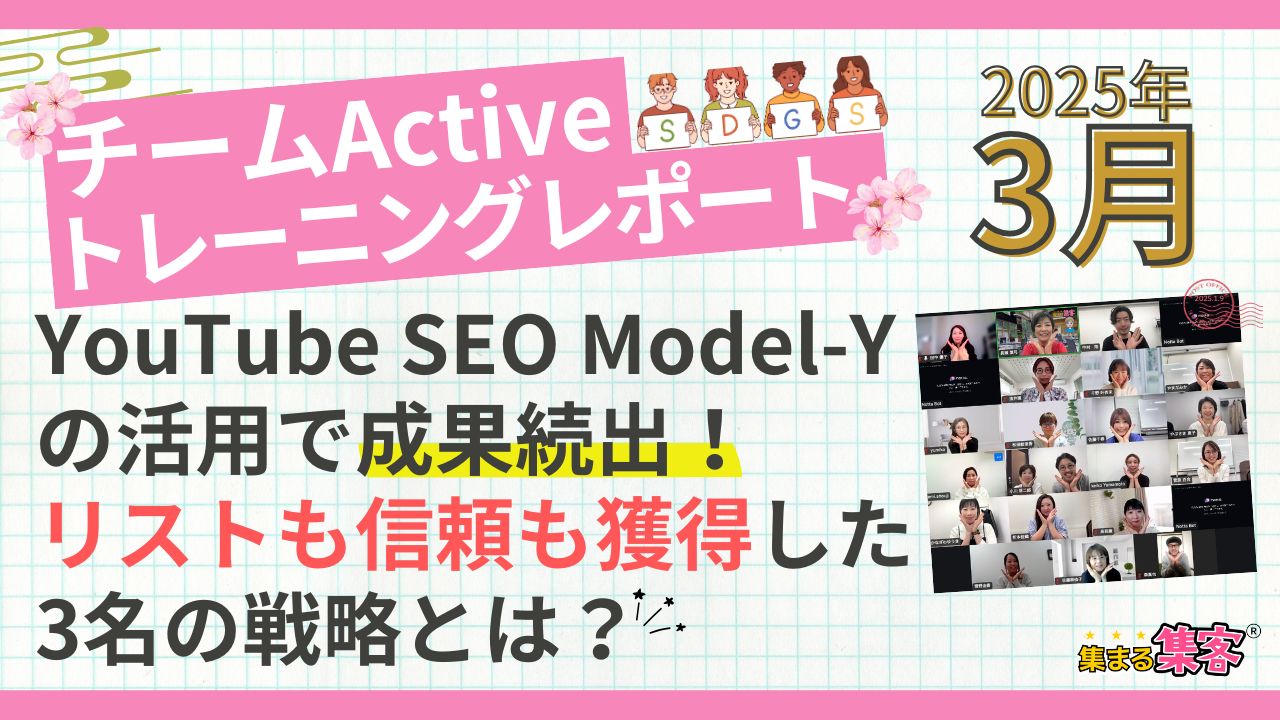
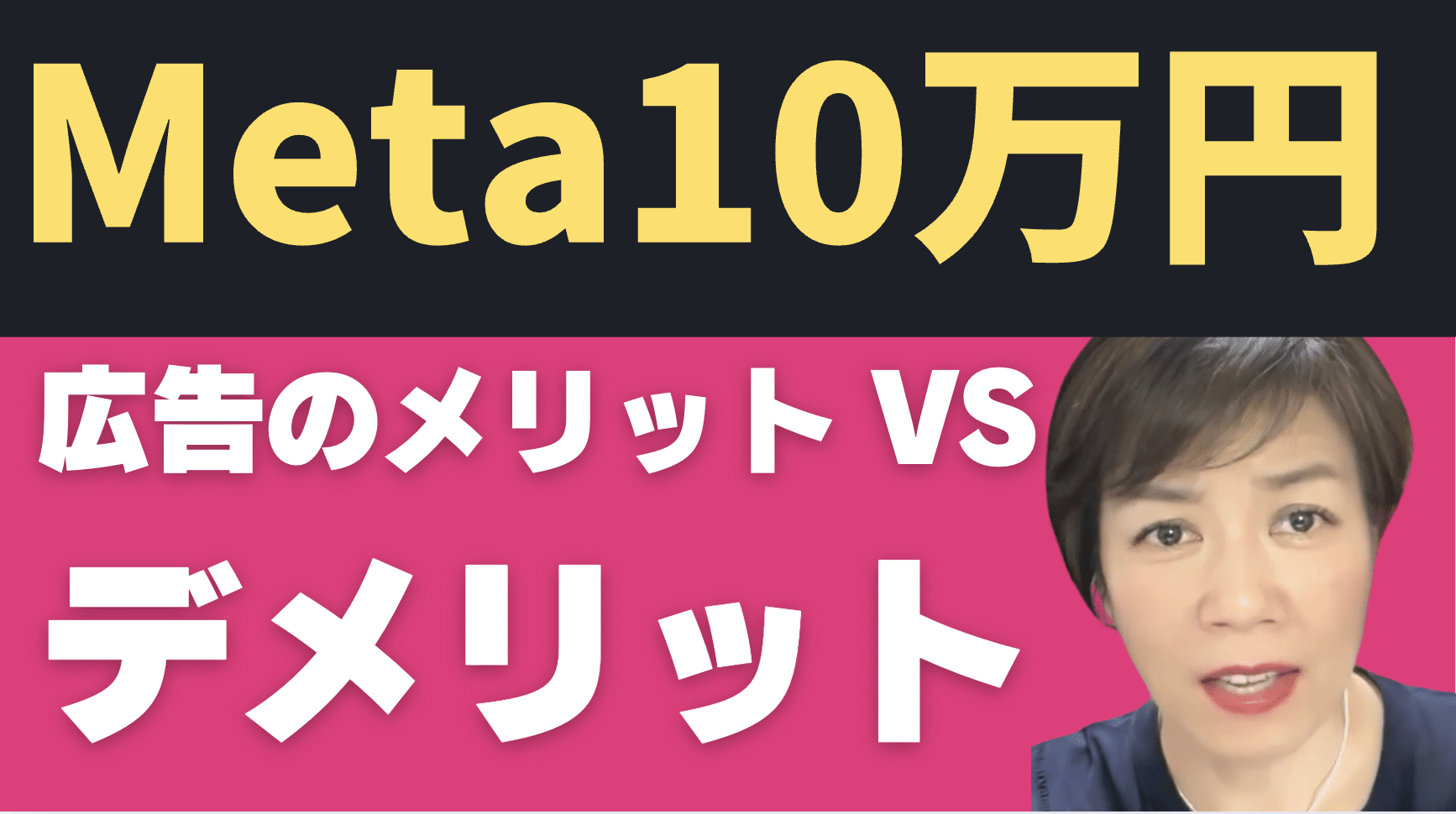
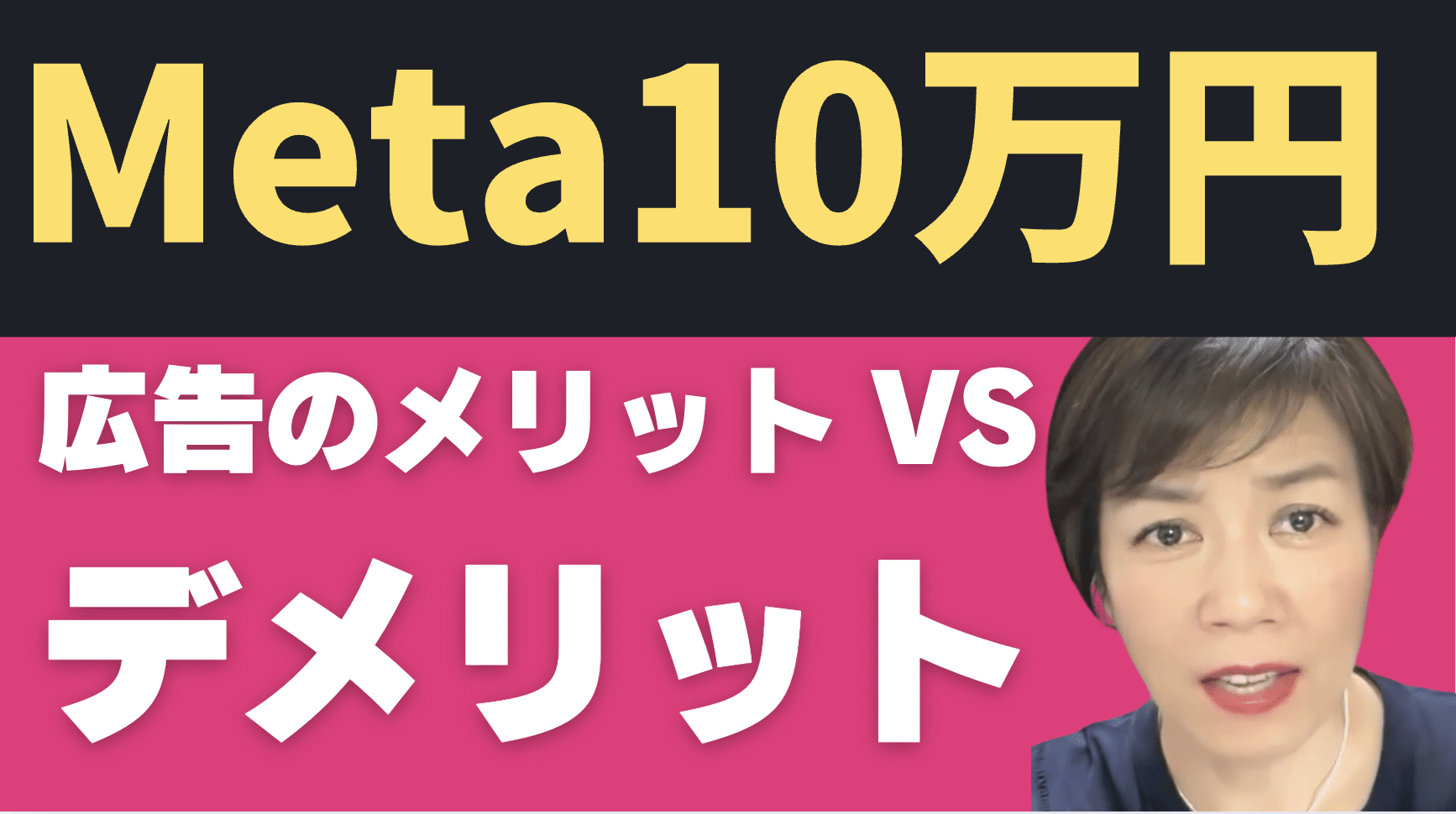
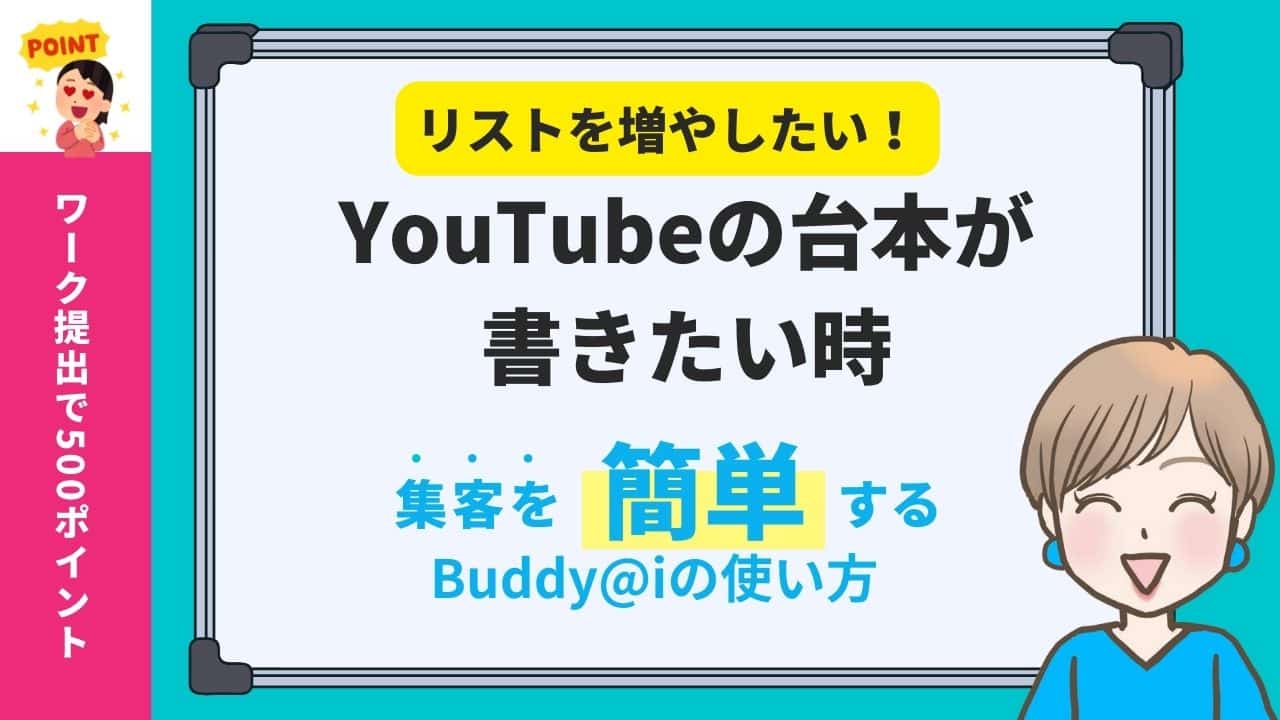
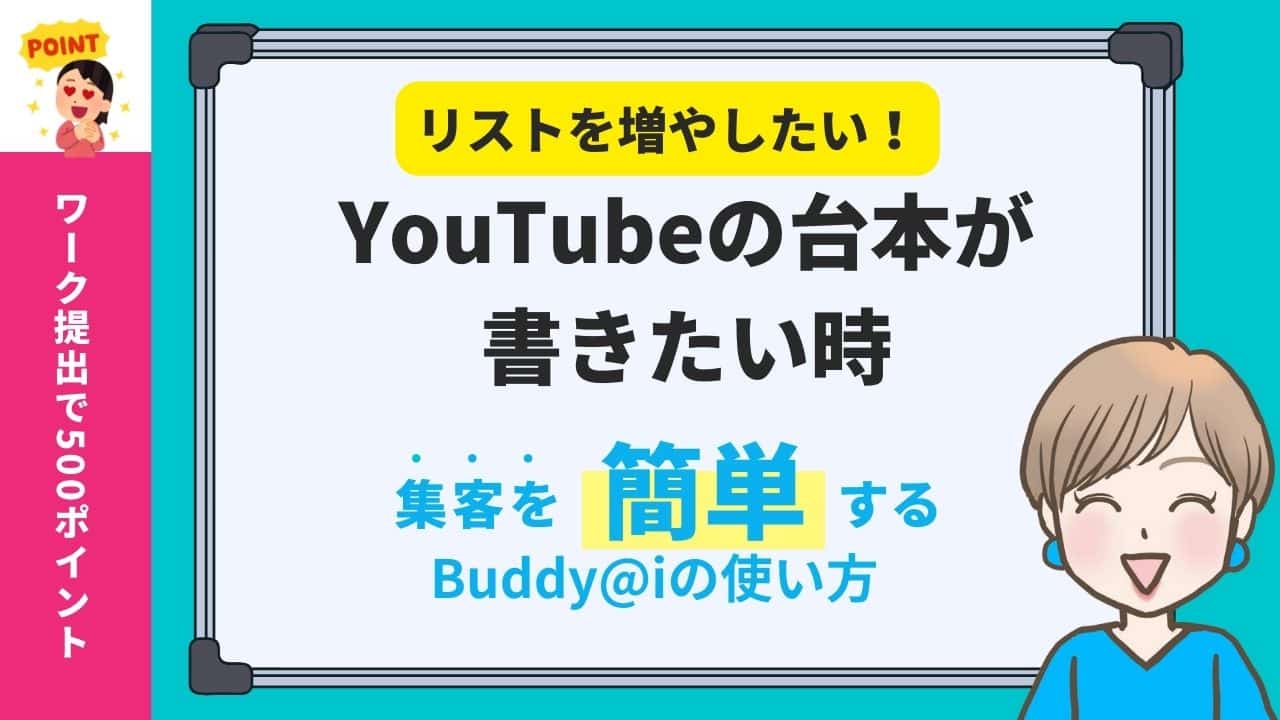
「再生回数が伸びない悩み」から卒業したいあなたへ
「クリック率も視聴維持率も上げてるのに、なんで伸びないの…」
そう感じているなら、「今の時代に合った届け方」に変えるタイミングかもしれません。
実は今、再生数が自然に伸び、検索され続ける動画を作る秘訣として注目されているのが「YouTube×AIの『Model-Y』ガイド」なんです。
「AIとかちょっと苦手で…」という方もご安心ください。
この小冊子は、動画のキーワード選定・台本・SEO設計まで全部“丸投げ”できるAI活用法を、女性起業家向けにやさしく解説しています。
🎁今だけ無料プレゼント中!
『講師・コンサル・カウンセラー・個人サロン女性起業家のための
YouTubeSEOで集客の時間を10分の1にする
噂のAI「MODEL-Y」必読ガイドBook』
✅ SNSに疲れた…それでも発信はやめたくない
✅ 「本当に届けたい人」に見つけてもらいたい
✅ 集客にかかる時間を大幅に減らしたい
そんなあなたにこそ、読んでいただきたい一冊です。
👇 無料ダウンロードはこちらから↓
